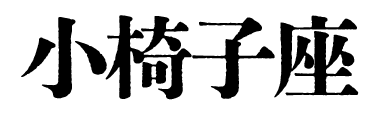新刊の様子はこんな感じです
テキストと枠装飾が銀に光ります pic.twitter.com/zaYanXrZ6z— 小椅子座🌙148: H40a (@koisuza) August 29, 2023
サークルメンバーの書き下ろし短編集です。
『CATHEDRA 月を詠う』
2023/09/03【COMITIA145】A5/モノクロ/本文50頁/カラー口絵有
- 《漫画》「ひとみのアルベド」:橋屋 燕
- 《漫画》「天の海」:ほふみ おと
- 《小説》「神無月」:北山 悠飛
▼SAMPLE▼
北山悠飛「神無月」冒頭4頁
月に神などいない、と。お偉い学者は言った。
彼等のご高説が国中に広まったのは、つい数日前からのことであった。
文明の発展に伴い学問を志す者たちの間で天文学とやらが流行していた近年。とうとう彼らの一部が、月と太陽に関する全く革新的で異例な学説を発表した。城下町ではその詳細が書かれた学術誌や新聞が瞬く間に売れた。国王並びに民は大いに戸惑った。
月には、神様が住んでいらっしゃる――それは古くからこの国の常識である。遥か遠くの空、月の上から、私たちを見守っているのだそうだ。誰もがそうと信じていた。ところがそれは誤りで、月の上には誰もいなくて、日々変化する月の形も、美しい月光も、太陽の光を受けてそう見えているだけに過ぎず、ただ自転しながらこの世界を回っているだけの大きな岩に過ぎないのだという。
人々は突然信仰の対象を失い、ある者は不安に駆られて教会へ押しかけ、ある者は嘘っぱちだと笑い飛ばした。国は直ちに学説を取り消すよう命じたが、学者たちは聞かなかった。強硬手段に出た王によって、学術誌は押収され焼き払われた。世間は随分荒れた。月とは切っても切り離せない関係にあるこの国において、この学説は、人々の拠り所の根本を揺るがす事態に相違なかったのである。……
* * *
新月のある夜、私は、いつも通り窓辺でバイオリンを弾いていた。
この世に生を受けておおよそ十九年。私にはかねてより、これを弾くしか能が無い。祖父が譲ってくれて以来、とりわけ音楽に身を投じてきた。いや、何も私ばかりでは無く、私の故郷には音楽を好む者が多かった。月の綺麗な夜は、村のあちこちから厳かな音色が絶えず、各々が家の明かりを消して、窓を開け、月光を浴びながら笛や弦楽器を奏でたものである。
入り組んだ高低差のある道沿いに、煉瓦造りの家が所狭しと並んだ城下町の片隅。それはそれは大きな町で、人口も多く栄えた町だが、貴族や政治家達の住む高層区とはうんと離れたこの場所は、雑然とした、ほとんど下層民の溜り場のような所である。元来、都とは縁の無い辺境の村出身だった私は祖父の形見のバイオリンと一緒に上京し、今はその古びた一角に身を寄せていた。
これを弾いている時、私の腕は弦と、心は音楽と一体化する。幼い頃から馴染み深いこの楽器を弾いている間だけは、全てが私の思い通りだ。そして、月の光の下、美しいその音色に恍惚と身を委ねる感覚。神様に見守られながら、音楽を捧げる喜び。それらはいつだって、私の貧しい心を慰めてきた。
曲を一通り弾き終えたところで手を止めて、冷めた紅茶を口に含む。いつもの癖で、開け放った窓から月を見ようと身を乗り出した。星が見えるだけの夜空を見上げ、今夜は新月だったと思い出す。ひと月に一度やってくる、神の現れない夜だ。
外は、物売りの声がとっくの昔に静まって、閑散としている。肌を刺すような冷たい空気が部屋に流れてきた。まだ秋も始まったばかりだというのに、冬の足音がすぐそこまで聞こえてきそうである。
月の無い夜空は、溜息の出るほどに心許ない。音色を聴かせる相手がいないのでは、心にぽっかり穴が開いたようで腕も鳴らない。……いや、始めから聴き手など、月にはいないのだった。私はそう思い直して嘆息した。ここのところ世間を騒がせている例の学説は、月を見ながらバイオリンを弾くのが習慣になっている私の生活にも影響を及ぼしていた。
私は外の空気を大きく吸い込んで、再び静かに腕を動かした。決して上等なバイオリンではない、それでも何年も弾いているそれは手に馴染んでおり、いつも懐かしい故郷の匂いを含んだ、華やかに伸びる良い音を出す。
ふと、窓の下から声がかかったのは、ちょうどその時だった。
「サンサーンスの白鳥」
聞き慣れたその声に窓から身を乗り出すと、この二階の窓の外、すぐ下の小道にツナギ姿の幼馴染の姿がある。軽く手を振り、大きく頷いてみせると、彼は満足そうに口の端を上げて笑った。
「仕事お疲れ様。上がる?」
「良いか?」
「鍵、空いてるよ」
私は言って玄関の方を指差す。彼は薄汚れた帽子をちょいと上げて応じ、ぞんざいな足取りで建物へと入っていった。
ギシギシと床を軋ませ階段を上がる足音を聞きながら、私はバイオリンを部屋の端の小椅子に置き、おもむろに立ち上がった。棚から欠けたティーカップを出してきて、先程からテーブルの隅にあるポットの中の、冷めた紅茶を入れる。部屋の扉が開かれ、彼、サクは疲れた顔に張り付けたような笑顔を浮かべて現れると、我が物顔で椅子に腰掛けた。
「毎晩毎晩バイオリン、ご苦労なことだ」
「お茶、どうぞ。ぬるいけど良い?」
「別に。砂糖は無いか?」
「悪いけど、切らしてるんだ」
言うと、彼は大袈裟に肩を竦めて残念そうにした。
「たまには甘い紅茶が飲みたいものだな」
「自分で買いなよ」
「……砂糖、高いんだよなあ」
そう嘆く彼の体躯は、元より線は細かったものの、村にいた時よりもどことなく骨ばっていた。私は自分の着ている、よれた古着のベストと、スカートのつぎはぎを見下ろして同じように嘆息した。
私たちは、貧しい下宿生だった。
彼と共に故郷を出て、もうじき一年になる。日中、私はこの近くの宿屋で女中としてほとんど雑用などの下働きをし、サクは小さな工場で職工として働き、ささやかな給料を手に、時に頼り合いながら切り詰めた生活を送っていた。
「なあラウラ。お前、ちゃんと働いてるか」
「働いてるけど、何故」
「俺が帰ってくる時間、いつも家にいるだろう」
「失礼な。朝早くから行ってるんだから。……最近は、夜には帰してもらってるってだけ」
私は会話中、ぼんやり外を眺めながら彼の言葉に応じた。
この建物は借り家で、私は二階、幼馴染は三階の部屋を借りて住んでいる。安い部屋なので、床は斜めっているし椅子は軋むし、空気は埃っぽく、ベッドの布団は年中薄く、天井からぶら下がる明かりは裸電球一つのみ――蝋燭でないだけましかもしれない。とにかく物こそ少ないので小ざっぱりしてはいるが、貧相さの否めない部屋であった。一つ救いだったのは、大家さんが良い人だったことである。大した手持ちの金も無く職にも就いていないという、家賃を払ってくれるかどうか見込めない田舎者二人をとやかく言いつつも受け入れ、面倒を見てくれた。加えて、こんな風に夜にバイオリンを弾いていても、一度も咎められたことが無い。これは大家さんだけでなく、近隣住民からもだった。この薄っぺらな壁ではどこへでも筒抜けのはずだが、興趣に捉えてくれているのだとしたら有難い。
「なるほど、練習するために仕事を早めに切り上げているのか」
「そう。……あんたは最近、どうなのさ。弾いてるの? チェロ」
私は、答えを知っていて尋ねた。彼がかねてより好んで弾くのはチェロで、当然彼もチェロを持って上京した。が、ここしばらく彼の部屋から、その音色が聴こえてきたためしが無い。
「……そうだなあ」
サクは僅かにバツが悪そうに目を逸らした。そして、紅茶を特に味わいもせずごくごくと飲み、飲んだくれのようにテーブルに突っ伏した。無造作に伸びた、癖のない栗色の髪が彼の顔を覆う。
「チェロを弾く時間を、睡眠に充てている」
「ふうん」
「仕事が忙しいんだよ。つまり……」
「つまり?」
いや、と小さく呻いて、彼は伏せたまま欠伸をした。
「音楽以外で、頑張りたいこともあるってことだ」
私は静かに彼の方を見遣った。
「……本気で言っているの?」
「ふん。お前は思わないのか? もう一年、ここで過ごして。俺だったらこんな所で一生貧乏暮しは嫌だぜ」
「確かに嫌だけど……そんなの、わかってたことだ。あんただって覚悟の上でここまで来たんじゃない」
「その通りだ。でも」
「私は、構わないよ。これさえ手放さずにいられるなら」
「……ろくな仕事に就かず、弾き続けるって?」
「そう」
「月に神がいなくても?」
私はつと口をつぐんで、身体を強張らせた。ちらと横目で見た彼は、身体を起こして頬杖をつき、こちらを見つめている。その面差しは真剣そのものだ。
言いたいことは次々と脳裏を駆け巡った。しかし、言葉にする気力が湧かずだんまりを決めると、彼は肯定と受け取ったらしい。小さく息をついて立ち上がった。
「……わかった。おやすみ。早く寝ろよ」
「……」
遠ざかっていく足音が扉の向こうに消えた。
私は、例の学説の話題にあまり触れたくはなかった。バイオリンを弾く意義の一つを否定されるのが嫌だからだ。たとえ気心の知れた彼であっても。
……